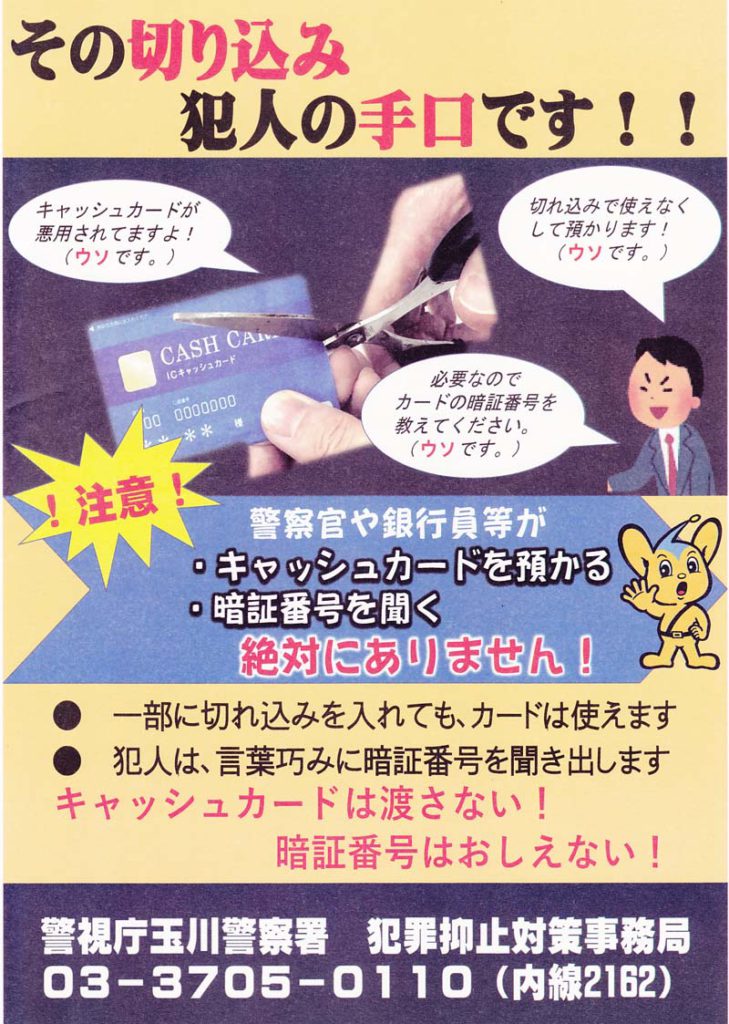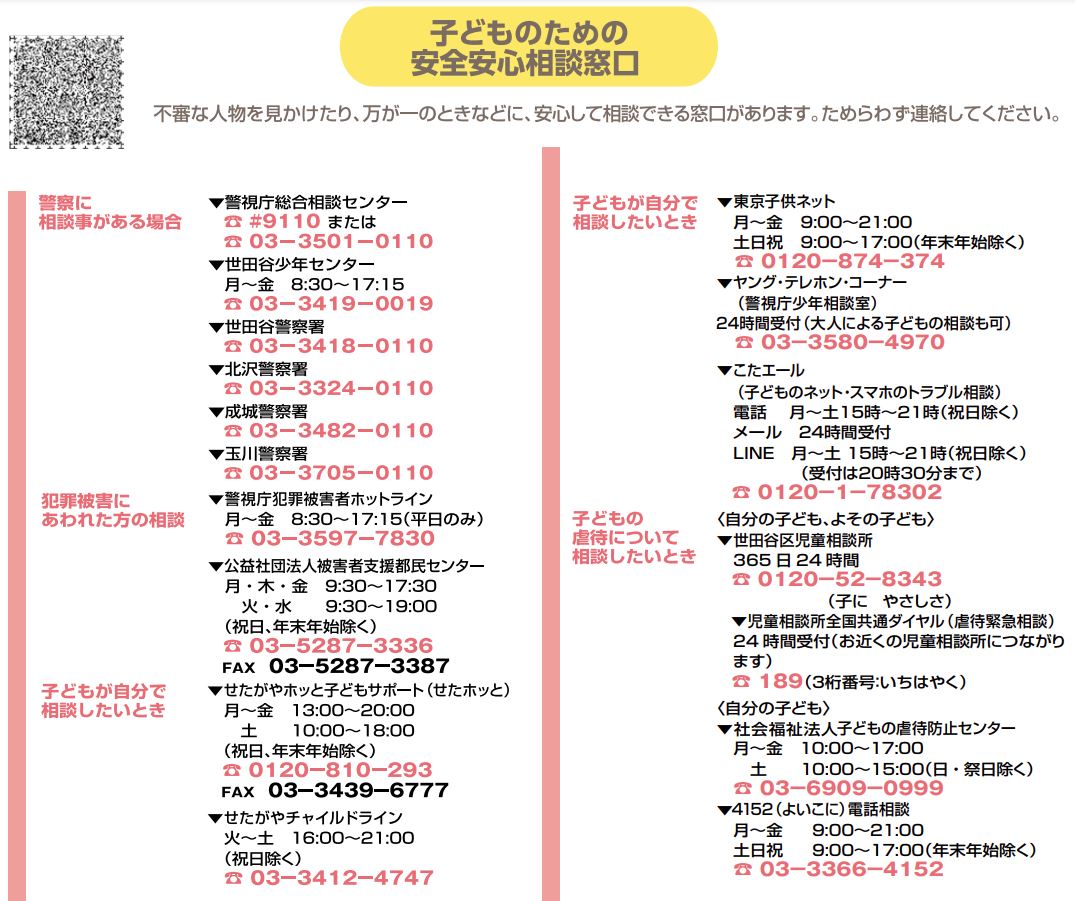★ 追記: 2023年12月26日 午後5時すぎ、東京都杉並区高井戸東で、女性と女の子の2人死亡。乗用車は歩道の脇にある自動車整備を行う店舗からバックで出てきたところ、2人をはね、そのまま片側2車線の道路を突っ切って反対側の歩道の柵に衝突
追記:『 東京・杉並区 親子はねられ死亡 「整備後の車を試運転しようとして下がった」自称整備士の男逮捕 』
★ 2023年12月19日 午後1時55分 ごろ、東京都世田谷区北烏山1の区道で、近くの小学1年生が友達4人と遊んでいる時に道路を渡ろうとしてトラックにはねられ死亡。
成城警察に逮捕された運転手は「わき見運転をしていた」「気づいたら目の前にいた」と供述
・日本テレビの映像
【事故】小1男児がトラックにはねられ重体 東京・世田谷区
・小1男児 トラックにはねられ死亡 運転手逮捕 東京(NHK)
・小1男児、トラックにはねられ死亡 運転手「間に合わず」 世田谷(朝日新聞)
・「気づいたら目の前にいた」トラックが公園から出てきた小1男子児童(7)をはねる 約2時間後に死亡 世田谷区(TBS)
・速報の現場映像(TBS)
・小1男児 トラックにはねられ死亡 東京・世田谷区 運転手の男逮捕(FNN)
◆ 事故のあった現場:地図 グーグルストリートビュウ
「北烏山一丁目オリーブ公園」付近
(管轄: 世田谷区成城警察)
この交通事故はどこでも起きておかしくありません。
またもういちど同様の交通事故が起きてもおかしくありません。
実際に私は「交通安全みまもりゴミ拾い」の活動中に、
町のなかで毎日、道路にとびだす小学生を目撃しています。
そして、
車の運転手も、車を走らせたまま、スマホやタブレットや、地図やカーナビや配達先名簿などの書類をみていて、前方を見ていない人がいることを現実に目撃しています。
「まちにいるおとな全員」でこどもをまもろう!!
「小学校一年生」はほんとうにちいさい子供です。
いくら何度も「車に気をつけよう」といってきかせても限界があります。
だから、こどものいのちを町の中にいるおとな全員で守りましょう。その努力を毎日つみかさねましょう!!
社会はぜんぶつながっている
おとな自身が交通安全をつねに気にしたり、交通ルールの基本をまもったり、「いのちを守る思いやり行動」を道路上でつねにしていれば、それは子供へのお手本になります。
こどもはお手本を何度も見ること、見かけることで、それが自然に身につき、マネるようになっていきます。
おとな自身が乱横断、ななめ横断、信号無視しない。
おとなが歩きスマホしない。スマホ片手運転しない。
おとなが耳栓イヤホンしない。
おとなが自転車で暴走しない。
おとなが歩道や駅や通路で「我れ先に」とひとを押しのけない。
自分が🚗クルマや🚲自転車で乱暴運転をしていれば、ある日べつの場所で自分の家族が、それとおなじような乱暴運転の危険や被害にさらされるかもしれません。
他人であってもおとなが子供をまもってあげる。いつでも、どこでも
自動車運転免許証を取得している子供は一人も存在しません。
免許取得の試験にでるようなこまかい交通ルールを子供たちは知りません。
ちいさな子供は「青信号をわたれば車はこない」と思いこんでいることも多いです。しかし実際のまちのなかでは、こどもが青信号で横断歩道をわたっているときでも、左折や右折で青信号の横断歩道内に自動車が走ってきます!
こういうとき、ちかくにいるおとな、からだの大きなおとなが、車がくる側に立って、手をあげて車の運転手にじぶんたち横断者の存在をはっきりわかるように伝えたり、アピールすることで、こどもを守れます。(運転手に対して笑顔で会釈すればケンカやトラブルになることはほとんどありません。)
もちろん運転手はだれかを車でひこうとして横断歩道に接近するわけではありませんが、人間はどんなおとなでも失敗したり、まちがえたりすることがあります。
実際に交通事故を起こした運転手の供述をきくと「うっかりしていた、ぼんやりしていた」「信号の色をまちがえた、勘違いした」「信号を見落とした、見ていなかった」という基本の基本のようなあたりまえのことができていない、失敗していることが原因となって死亡事故が起きている現実があります。
横断歩道があってもなくても、信号があってもなくても、かならず、自分自身の目で、左右とまえとうしろの安全、車の接近をたしかめる!
自分自身のからだを、さいごは自分のちからでまもる!
町の中にいるおとなは、その体の大きさや強さ、運動神経を、自分よりも小さな人やこどもや高齢者を守ることにつかいましょう!!
体の強いおとなは、耳栓でイヤホンをきいて歩行したり、歩きスマホしながらでも同時に道路状況を確認して自分の身の安全を確保できるかもしれません。
しかし、その運動能力、運動神経があるのならば、どうかその「余力」を自分が得するために使うのでなく町いる、そのとき自分のまわりにいるひとたち、自分よりも弱い人たちのためにつかってほしいと、私は願います。
社会はすべてつながっています。
まちのなかには、歩道をまっすぐ歩く、普通に歩くということだけでも精一杯だったり、杖をつかったり、足をひきずりながら大仕事として苦労して一歩づつ歩いている高齢者や、ケガや病気の人もいます。
幼児やこども、大きな荷物をかかえてよろめきながら進むひと、ベビーカーを押しているお母さん、自転車をふらふらしながら一生懸命こいで周囲まで見る余裕や体力のない人もいます。
なかには、一見すると体の大きな健康な成人にみえても、身体や精神の障害をかかえている方もいます。
歩道や町のなかでは、
つよいほうが、よわいほうに ゆずる!
ゆずるひとが つよいひと。
道路上で子供をまもる具体的な注意点
まちのなか、道路上でこどもが車にひかれそうな危ない状況を見かけることはだれにでもあります。
そのときどう動き対処するのが最善なのかは状況次第で、そのひとが判断するしかありません。
よかれ、と思ってとった行動が逆に危険を高めてしまうことだってありえます。
そうならないように、健康で体力のある「こどもをまもる立場のおとな」は、なるべく危険な状態が発生するそのもっとまえから、危険がおきる事前から、道路上の状況をつねによく観察しておけば、ぎりぎりの切羽詰まった状態になるまえに、余裕をもって事故防止、予防のための行動をとることができます。
たとえば、まだ危険はまだ発生していないけれど、歩道をあるいているとき、前方に親子連れが歩いていて子供が車道にちかい側をうろちょろと歩いていたら、その後ろをついて歩いている時(他人であっても)に、自分が車道と子供のあいだに体をいれて、もし子供が歩道の切れ目で車道に飛びだしそうになった際は、バリア、とおせんぼ、することができる位置どりをする、などの事前行動がとれます。
特に、
・小学生低学年よりもちいさい子供がひとりで歩いている時。
・おとな一人がこども二人以上を連れ歩いている時。
・荷物などもって親がうしろでこどもが離れて先を歩いたり走っている時。
・横断歩道で信号待ちしてるとき子供が車道ちかくで立っている時。
そいういう時は、他人であっても事前にさきまわりして、子供の安全のための「ガードレール役」をはたしてあげましょう。
信号機が青色に変わった途端それをスタートダッシュの合図にしようという姿勢でまちかまえる子供の姿はよく見かけます。
信号が赤に変わってもまだつっこんで進んでくる車の姿も見かけます。
ある時、このタイミングが重なってしまったら簡単に交通事故が起こってしまいます!
おとながこどもに
「車のおとなも信号無視してくるひとかならずいるからね!」
「ぼくたち歩行者の信号が青色に変わっても、車がよこからすすんでくる(左折車、右折車というのがある)からね!」
と、車道と歩道のあいだに「とおせんぼ」して間に立って、子供達を守りながら、おしえてあげましょう。
急に子供に大声で注意するのは危険が増す場合がある
子供は急に車道にとびだしたり、自転車でうしろを振り返ってたしかめずに反対側に移動したり、信号無視をしたりします。
しかしそのとき町の中で、急に知らないおとなの人が大声でさけんで交通安全を注意したら、子供はびっくりして車道のまんなかで立ち止まってしまったり、ふりむいて自転車のバランスをくずして転んで、よけいに危険な状態になってしまうこともあります。
子供が車にひかれそうな状況が発生して、そのときどうするのが一番よいのか正解がなにか実際にはわかりません。しかしそのとき一番ちかくにいる大人たちがその瞬間に判断して、対処するしかありません。
私の経験上、交通事故が起きそうな状態になったときは子供の側に注意(声かけ呼びかけ)をするよりも、まず、車と子供のあいだに自分の体をいれる位置どりをしてみせて(もちろん自分の身の安全も考えながら)「せまってくる危険な脅威である車の運転者側に対してアクションをおこす」のが事故回避につながることが多いような気がしました。
あぶないときは、運転手、車の側へ大きく手をふって知らせたり、まずブレーキをふませる。手や指をつかった大きくわかりやすいジェスチャーで運転手から死角となっている場所に子供や危険な障害物があることを伝えたり、必要なら大きな声をかける(ただし、声は大きく出しても言葉は選んで。短い言葉でつたわりやすく、怒るような言葉でなく命の危険を心配する真剣かつ尖っていない注意喚起の言葉を。)
危険をさけることができて、そのあと子供に対して道路で「いのちをまもるためにどうしたらよいか、よかったか?」を指導する際は、必ずまず自分たちがガードレールやガードパイプ、車止め柱にまもられた、歩道内や安全な場所で、ほかの歩行者の通行のさまたげにならない空間に退避してから、そこでこまかい説明や話をして子供達に交通安全についてきかせてあげましょう。
命の危険がある瞬間に立ち会った場合は、他人であっても他人の子に「命のまもりかた」や交通安全の話をしてあげられる地域社会のほうがよいと、私はかんがえています。
(もちろんそのためには、その指導をする人自身がふだんから交通安全をまもり、まちの住人としてふだんから地域の信頼を得る努力も必要だと思います。)
道路上で「子供のいのちをまもる」行動には、それをする側にも危険がともないます。
だからそれを誰にでも安易にすすめることはできません。
しかし、おとな全員がそれぞれの場所から、自分のできる範囲で自分の安全を確保しながらでも、できることは色々あります。
駐車場付近でも命を救えます
運転手ひとりには眼が二つ 👀 しかなく、運転席からは見えない「死角」がたくさんあります。
もし駐車場や路上で、駐車している車がうごきだそうとしている時、車のうしろや見えないところにちいさな子供いたら、自分が誰だろうとどういう立場だろうと勇気をだして大きな声や身振りてぶりを使ってすぐに運転手にそれを知らせて一旦うごくのをやめさせたり、子供が安全な場所へ移動するのを手伝ったりしましょう!
★ 実際に毎年、住宅地や商業施設の駐車場で子供や高齢者がひかれて死亡する交通事故が起きています。また、高齢者の急発進や駐車時にブレーキとアクセルをまちがえて店舗建物にとびこんだり、崖や川や海に転落することもあります。
追記: 2024年1月21日、商業施設の駐車場で3歳の女の子が乗用車にはねられ重体 岡山・倉敷市 KSB瀬戸内海放送
車は駐車している状態から発進するときは、まわりのひとに「いまからこの車はうごきだしますよ!」と知らせる意味で、かならずウインカーをつけましょう!(つけないで動き出す車を町のなかでよく見かけます。ウインカーをつけるのは自分のためでなく、まわりにいるひとに知らせるためです。)※ 参考
なるべく路上駐停車はしないほうがよいですが、やむを得ずする場合は「ハザードランプ」を点滅したままでつけて車の存在を知らせましょう。また、交差点や建物角でみえないような場所に駐車するととても危険です。見通しのよい場所をえらびましょう。
(高齢者が無駄に大きなサイズの車を買ってしまい、買い物時に駐車場にいれることができなくて路上駐車を常にしている光景も見かけます)
駐車場や路上駐車している車内に子供がとじこめられていることもありえます。こどもの通園バスなどでもとじこめや「降ろし忘れ」があります。
子供が車にとじこめられると車内温度が上昇して熱中症になって死亡してしまう事故が複数おきています。冬の雪国なら凍死事故もありえます。
おとなが町を歩くときに耳栓イヤホンで音楽をきいたり歩きスマホに夢中にならずに周囲に気を配っていたら、子供たちの「たすけて!!」という声に気がつけるかもしれません。
「ひょっとしたら とじこめかも…?」と思ったら、まちがえであることや、余計なお世話と言われることをおそれずに、駐車場係員やその家の人に声をかける行動を自分自身で勇気をもって実行しましょう。
ひとの命のことをおもって真剣に行動した結果のまちがいは、町のひとも警察もみんな許してくれます。
※「道路交通法施行令第二十一条」などに明確な記載がないなどの理由で「発車、発進時にウィンカー(方向指示器)を出すべきかどうか議論」になることもありますが、バス発車時のウィンカー運用でもわかるとおり、つけて周囲に発進を知らせるほうが安全なのはあきらかです。今後、そのあたり道路交通法の改正や条例で補われたりするかもしれません。
(★もし私の知識勉強不足ですでに法律の規定が2023年12月現在ある場合はご指摘、教えていただけましたらたいへんありがたいです。)
別の話として、方向指示器が見えにくい伝わりにくい車両デザインという問題もあると思います
交通安全は、毎日のつみかさねで、からだにしみこんでいくものだと思います。
「歩き」の時でも信号を正しく守って待つクセをつけて、それが体にしみつくと信号待ちの時間にイライラすることがなくなります。自然と意識のなかに「安全な歩道内」と「危険な車道上(横断時)」と区別が明確になってきて、車道にあしを一歩おろす前にあしをとめて左右を確認する習慣がつきます。
横断歩道以外のみちをなるべく渡らないですむルートえらびも自然にできるようになります。
おとなが町のなかで常にお手本をみせて子供達に「道路というものは 命の危険があるこわい場所である」ことを本気で知らせ、
とくに小さな子供たちには、何度も何度も、具体的に、道路では、歩道では、横断歩道では、どうしたらよいかを 100回でも1000回でも繰り返し伝えていき、身体にしみこませる。
子供から「うるさいなあ」と憎まれ口を言われても、無視されても、親から余計なお世話だというイヤな表情をされても、本当に命の危険があると思った時は、何回でも言う。伝える。他人であっても。なにか損をしたような気分になっても。言う。
(※バランスを考えて出過ぎない言い方や、言葉づかいの配慮も必要ですが。「説教」にならずに「いのちを心配する言い方」「実際に起きた交通事故の例をつたえる言い方」がよいと思います)
地域のおとながこどもたちを心配するこころ、きもちが、本当に伝わるまでには時間がかかります。相手によっては、何十年か後、子供が大人に成長しておとなになって自分の家族やこどもを持つようになってからはじめて気がつくかもしれません。
それでも、子供時代に地域のおとな、まわりにいるおとなが「じぶんたち子供のいのちを心配してくれた、まもろうとしてくれた」という事実は、きっとなにか社会の良い面をひろげていったり、良い方向へひっぱったりすすめていくのに役にたつのではないかという気がしています。
町にいるおとな全員で、こどもたちの命を交通事故からまもっていきましょう。
悲しい事故のニュースを見て悲しむだけでなく、
悲しい事故のニュースが起きるまえにそれをふせぐ努力を積み重ねる。毎日。町内のどこでも。
まちにいるおとな、みんなの手で!!
追記★ 2023年12月25日 午後4時すぎに、岡山県倉敷市で、自転車に乗っていた小学2年生の男の子(7)が車にはねられる交通事故がありました。【 RSK山陽放送ニュース 】
追記★ 2023年12月25日 午後6時半ごろ、静岡県浜松市有玉北の交差点で軽自動車と自転車が出合い頭に衝突する事故がありました。自転車に乗っていた15歳の女子高校生が病院に搬送されましたが頭を強く打ち意識不明の重体【 静岡第一TV 】
全国のどこであろうと子供が犠牲になる交通事故のニュースを知るたびにおなじように胸がしめつけられ涙が浮かんできます。
じぶんの住んでいる東京世田谷区だけ安全であればよいわけでなく、日本のどこであろうと子供が死んでほしくない。回復不可能なケガなどを負ってほしくない。
おとなが、こどもをまもる!
つよいものが、よわいものを まもる!!
どこであっても。